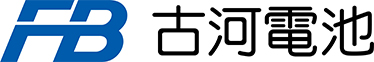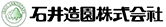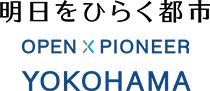セッション
日英同時通訳あり
DAY 110.23 Wed.
アジアの都市によるリバースピッチ/日本企業によるビジネスピッチ ~都市課題の解決に向けたビジネスマッチング~
GREEN STAGE 10:40-12:00
英語・日本語
英語・日本語
経済成長が著しいアジアの市場。多くの日本企業が関心を寄せる一方、アジアの諸都市においては急激な都市化の進展や都市部への人口集中などにより、都市問題などの解決に向けたニーズが高まっている。本セッションでは、インフラや省エネルギー等、脱炭素分野を中心に都市が抱える共通課題の解決に向け、複数のアジアの都市が自らの都市課題を発表し、日本企業がソリューションやアイデアを提示する。
あわせて、多くの都市と経験・知見の共有を進め、脱炭素化を促進すべく、OECDが横浜市の脱炭素に関する取組を分析する。
ラウニオン州サンフェルナンド市(フィリピン)、プノンペン市(カンボジア)、サンカルロス市(フィリピン)、マンダウエ市(フィリピン)インドネシア(バリクパパン)、株式会社京三製作所、JFEエンジニアリング株式会社、株式会社村田製作所、サントモ・リソース株式会社、カナデビア株式会社(旧・日立造船株式会社)
次世代エネルギーの活用による脱炭素イノベーションの創出
GREEN STAGE 13:10-13:55
カーボンニュートラルの実現に向けては、省エネや電力の再エネ化を進めるとともに、水素等の次世代エネルギーの活用や新たな脱炭素イノベーションの創出が期待される。横浜市では、エネルギー関連産業、製造業、物流等が集積する臨海部を中心に、水素、アンモニア、e-methaneなどの次世代エネルギーに関する研究開発や実証が進められている。 昨年度には、次世代エネルギーの需要創出・供給拡大や脱炭素に資する先進的な技術の研究開発に向けた連携を図るため、多様な市内企業・団体や学識経験者等から構成する「横浜脱炭素イノベーション協議会」を設立した。本セッションでは、協議会会員でもある企業等から、先進的な技術やナレッジを共有する。
-

経済ジャーナリスト -

フロンティアビジネス本部
本部長補佐/兼戦略統合本部 経営企画部 技術戦略室 室長 -

水素・カーボンマネジメント技術戦略部
革新的メタネーション技術開発グループマネージャー -

脱炭素・GREEN×EXPO推進局カーボンニュートラル事業推進課長
EVは本当に実用的なのか ~モビリティの2030年を考える~
GREEN STAGE 14:05-14:50
日本語
日本語
脱炭素に向けたグローバルな取組が進む中、大きな転換期を迎えている自動車業界。電気自動車(EV)の開発に伴い選択肢が広がり、世界的にEV普及率は高まっている。
日本でもマイカーを中心にEVの販売シェアが伸び、付随インフラである充電器の導入拡大も求められている。あわせて、マイカーに比べてハードユースであるバスやトラックなどの商用車についてはEV化が進展しておらず、モビリティ領域全般のEV化に向けた課題となっている。
本セッションでは、世界のモビリティの最新動向に加え、EVのインフラ分野での企業の取組なども交え、EVの可能性をディスカッションする。
市内および海外大学の学生による都市課題解決戦略の共同提案発表:インフォーマル市街地におけるレジリエンス
GREEN STAGE 15:00-16:00
英語
英語
横浜市立大学は、横浜市が主催するアジアスマートシティ会議に継続的に参加し、毎回様々な形で教職員、学生が携わっています。本セッションでは、横浜市立大学が2009年9月に設立したIACSC(International Academic Consortium for Sustainable Cities)において実施した、東南アジアの大学との都市課題解決戦略の共同提案の成果を参加学生が発表します。
今年(2024年)の夏、横浜市立大学学生は、IACSCのメンバーである、フィリピンのフィリピン大学およびインドネシアのハサヌディン大学との共同で、災害リスクの高いインフォーマル市街地(≒スラム)におけるレジリエンスのある安全なコミュニティ構築をテーマに、フィリピン大学ディリマン校でワークショップを実施しました。
本セッションでは、ワークショップの成果をもとに、参加学生が都市の持続可能な発展・成長のために居住や災害対策はどうあるべきか、洞察と提案を発表いたします。
-

都市社会文化研究科 教授、グローバル都市協力研究センター まちづくりユニット ユニットリーダー -

グローバル都市協力研究センター特任助教 -

社会基盤部 都市・地域開発グループ第二チーム 調査役 -

社会基盤部 都市・地域開発グループ第二チーム ジュニア専門員 -

ウェルビーイングを向上する都市デザイン
GREEN STAGE 16:15-17:15
日本語
日本語
一般社団法人スマートシティ・インスティテュートでは、スマートシティや都市デザインの取り組みが、単なるテクノロジーの実証にとどまらず、市民のウェルビーイング向上に貢献することが重要だと考えている。その影響を可視化するため、地域幸福度(Well-Being)指標を開発し、横浜市を含む、日本の多くの都市で市民のウェルビーイングを調査してきた。また、昨年度から横浜市立大学と協働しながら、ウェルビーイングの鍵となる「生きづらさ」は、物理的な都市空間だけでなく、バーチャル空間にも大きな関わりがあると確信している。都市空間。バーチャル空間がウェルビーイングにどのように影響を与えるかは、海外でも注目されるテーマだ。 今回のセッションでは、横浜や韓国を先端事例として、市民のウェルビーイング向上を目指す公共空間やサイバー空間のあり方について議論する。
-

-

医学群教授・研究・産学連携推進センター拠点事業推進部門長 -

業務担当官 -

教授
- 主催
- 横浜市
- 後援
- 内閣府
- 外務省
- 財務省
- 経済産業省
- 国土交通省
- 環境省
- CITYNET
- 国際農業開発基金 (IFAD)
- 国連開発計画(UNDP)駐日代表事務所